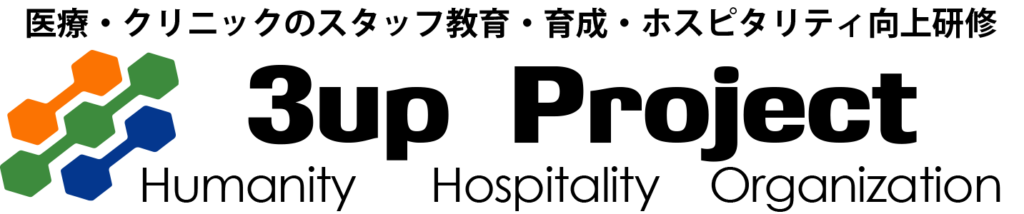チームビルディングは、形成期、混乱期、統一期、機能期、散会期という5つのタックマンモデルで構成されています。
散会期は、いわばチームビルディングにおけるチームの最終段階であり、こちらの段階をどう迎えるかで、成功か否かが変わってきます。
今回は、理想的な散会期の迎え方について解説します。
散会期とは?
散会期とは、これまで同じ目的に向かって業務に取り組んでいたチームを解散し、チームビルディングの成否を確認する時期を指しています。
Adjourning(アジャーニング)とも呼ばれます。
リーダーの手腕が問われる混乱期、すべてのチームメンバーが活躍する機能期などを問題なく乗り切ることで、ようやくこちらの段階にたどり着くことができます。
| フェーズの定義 | 次のステップに進むポイント | |
| 散会期 | チームが解散する段階 | 総合的な観点からチームビルディングの成否を確認する |
チームビルディングにおける散会期の理想的な迎え方3選
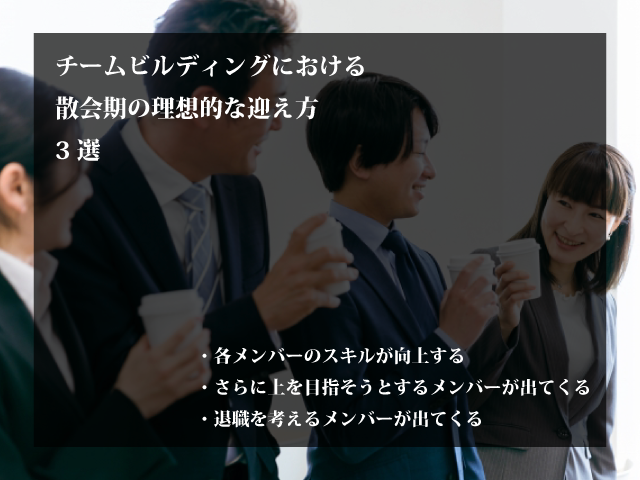
チームビルディングが散会期を迎えたとき、チームに以下のような特徴が見られる場合は、これまでのプロセスが間違っていなかったと証明することができます。
・各メンバーのスキルが向上する
・さらに上を目指そうとするメンバーが出てくる
・退職を考えるメンバーが出てくる
各メンバーのスキルが向上する
チームが散会期を迎えるということは、これまでチームビルディングを行ってきたメンバーがそれぞれ別の目的やミッションに向けて動き出すということです。
そのため、基本的には解散後も、同じクリニックにメンバーが残ります。
また、散会期の時点で各メンバーのスキルが大きく向上している場合、クリニックにとっては大きな戦力アップとなります。
さらに上を目指そうとするメンバーが出てくる
散会期を迎えたチームメンバーの中には、目的を達成したことによって心境に変化が生まれるメンバーもいます。
例えば、医師としてさらに上を目指すために独学でスキルを身に付けようとしたり、資格取得を目指したりといった変化です。
このような変化も、当然クリニックにとってプラスに働きます。
退職を考えるメンバーが出てくる
チームビルディングの散会期には、ミッションの達成を機にクリニックを退職するメンバーも出てきます。
こちらは、キャリアアップを目的とするものだけでなく、医師として、もしくは別の職業として、新しくチャレンジしたいことが出てきたというケースも含んでいます。
もちろん、優秀なメンバーが退職することはクリニックにとって残念ですが、こちらはチームワークを通じ、個々が成長したという証であり、散会期の迎え方としては理想的だと言えます。
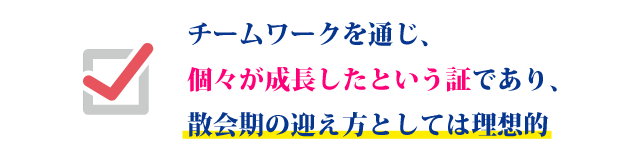
散会期においてリーダーが意識すべきこと

チームビルディングが散会期を迎える際、リーダーである院長先生は、メンバーに対し激励や感想を述べることを忘れてはいけません。
こうすることにより、メンバーは満足感を味わうことができ、次の業務に対するモチベーションもアップします。
もちろん、このような激励や感想については、散会期を迎えることをきっかけに退職するメンバーに対しても伝える必要があります。
「別のところに行っても頑張って」と激励したり、これまでの活動についてポジティブな感想を伝えたりすることで、メンバーは「また機会があれば同じチームで仕事をしたい」と思いながら、気持ち良く活動を終了させることができます。
まとめ
ここまで、チームビルディングにおける理想的な散会期の迎え方について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
クリニックのチームビルディングは、ただ単にチームの目的を達成すれば成功とは言えません。
散会期におけるメンバーの成長や変化を確認できて、初めて成功したと言えます。
また、よりメンバーの成長を願うクリニックは、3up Projectを活用し、人材育成・教育に役立ててください。