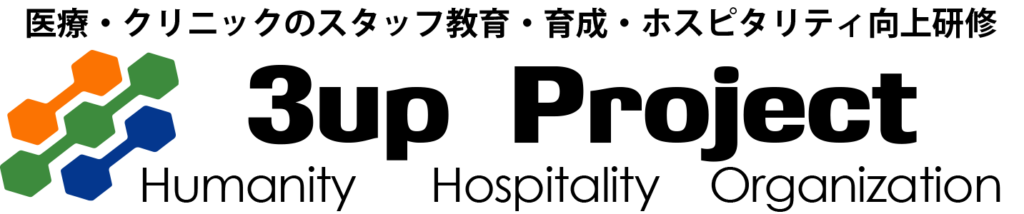クリニックのチームビルディングにおいて、院長先生はメンバーの模範にならなければいけません。
そうしなければ、素直に意見を聞き入れてくれない可能性があります。
また院長先生は、メンバーに対する言葉遣いにも気を付けなければいけません。
今回は、院長先生がDワードを使用するデメリットについて解説します。
Dワードの概要
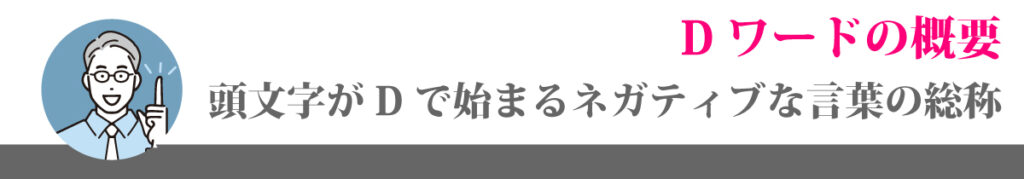
Dワードは、頭文字がDで始まるネガティブな言葉の総称です。
具体的には以下の言葉が該当します。
言葉 効果
でも 相手の意見を否定するニュアンスが強く、議論を遮る印象を与える
だって 相手の意見や言動の理由を説明する際に自身の正当性を主張したり、言い訳したりするニュアンスが含まれる
どうせ 「どうせ無理だ」のように、プロジェクトの成功を諦めるようなネガティブな発言につながる
ダメ 「それはダメだ」「ダメなことだ」といった直接的な否定や拒否のニュアンスを含む
院長先生は、複数のメンバーを預かる立場として、できる限りこれらの言葉を使用しないことが望ましいです。
チームビルディングでDワードを使用するデメリットは?
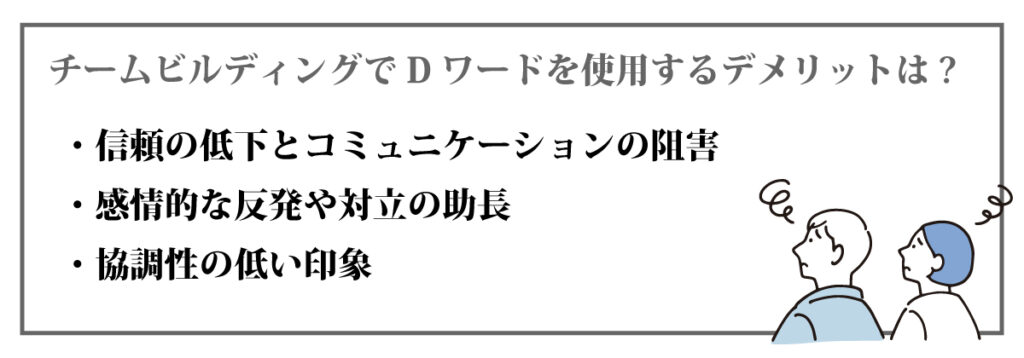
チームビルディングで院長先生がDワードを使用すると、以下のようなデメリットにつながります。
・信頼の低下とコミュニケーションの阻害
・感情的な反発や対立の助長
・協調性の低い印象
各デメリットについて詳しく説明します。
信頼の低下とコミュニケーションの阻害
相手の提案を否定する形でDワードを使用すると、提案者のメンバーは次回から意見をためらうようになり、信頼関係が揺るぎます。
またオープンなコミュニケーションが遮られ、結果的にチームのパフォーマンス低下につながる可能性があります。
つまり院長先生がDワードを使用することで、メンバーの模範になれず、正しく教育するのが難しくなるということです。
感情的な反発や対立の助長

チームビルディングにおいて、院長先生が「でも」「だって」といった言葉を多用していると、メンバーは自身の意見を否定されたと感じます。
こちらが感情的な反発を招き、関係が悪化することが考えられます。
またDワードを使用すると、チームビルディングにおける議論が勝ち負けの構造になりやすいです。
そのため建設的な議論から対立的な関係に発展しやすく、同じ目標に向かって協力しなければいけないチームビルディングにとって、これは良くないことです。
協調性の低い印象
常に院長先生がDワードを使ってメンバーと会話する場合、協調性がない、あるいは非協力的であると見なされる可能性があります。
院長先生は、もっとも協調性を持って複数のメンバーと関係を構築しなければいけません。
そんな院長先生が他のメンバーに協調性を否定されると、チームビルディングは破綻してしまうおそれがあります。
Dワードを避けるためのポイント
院長先生がDワードの使用を避けるには、メンバーとの会話において「はい」「なるほど」といった肯定的な言葉から始めましょう。
こうすることで、より建設的な議論に進みやすくなります。
またすぐに反論せず、一度メンバーの意見を最後まで聞き、内容を理解するように努めることも大切です。
最後まで意見を聞けば、当初否定的だった気持ちが変わるかもしれません。
ちなみにDワードとは真逆の言葉に、Sワードというものがあります。
例えば「その通り」「すみません」「そうなのですね」などが該当し、こちらはメンバーに肯定的な印象を与えるため、適宜使用すべきです。
もちろん、意味が同じであれば言い方を変えても構いません。
まとめ
院長先生が複数のメンバーを束ね、チームビルディングの目標を達成することは、決して簡単ではありません。
しかし、メンバーへの配慮によって信頼を得ることができれば、複数のメンバーが同じ方向を向いてくれる可能性が高いです。
またメンバーへの教育がもっと必要だと感じるのであれば、3up Projectなど外部のセミナーも活用しましょう。