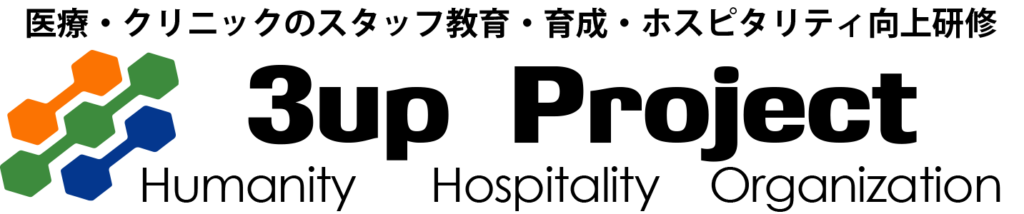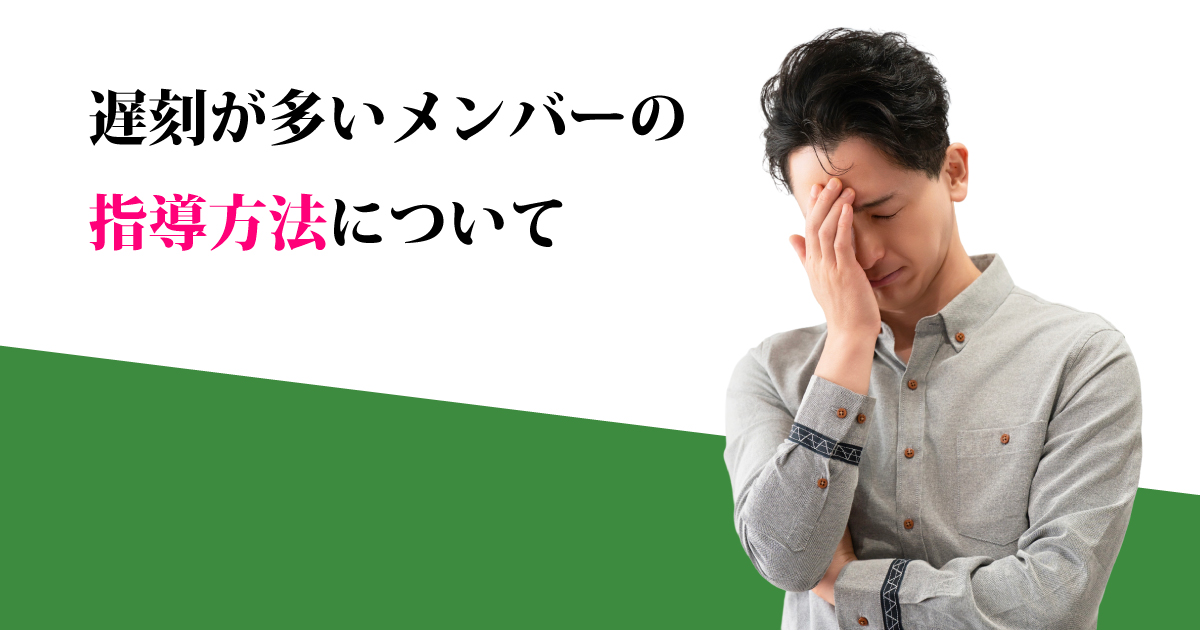クリニックのチームビルディングにおいて、遅刻が多いメンバーはチームの規律を乱すおそれがあります。
そのため、院長先生はきちんと指導し、全員が同じ時間に業務をスタートさせられるようにしなければいけません。
今回は、遅刻が多いメンバーの指導方法について解説します。
遅刻が多いメンバーの指導方法4選
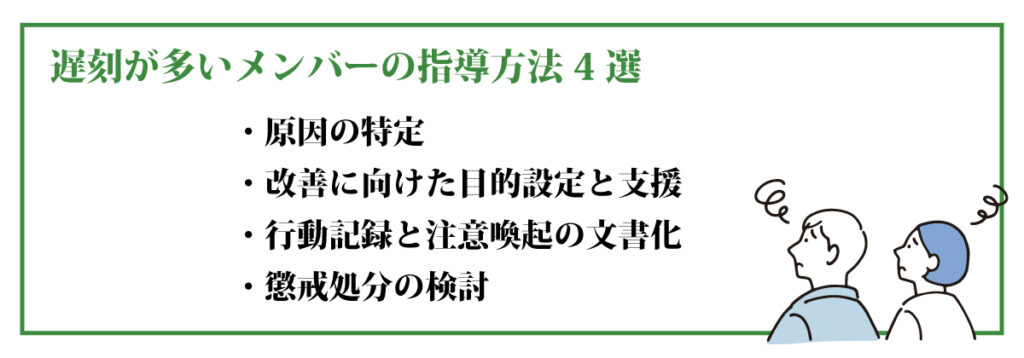
頻繁に遅刻してくるメンバーがいる場合、以下のような指導方法を採り入れるべきです。
・原因の特定
・改善に向けた目的設定と支援
・行動記録と注意喚起の文書化
・懲戒処分の検討
各項目について詳しく説明します。
原因の特定
遅刻が多いメンバーを指導するには、まずその原因を特定しなければいけません。
具体的には、遅刻が多いメンバーに対して個人面談を行い、相手の言い分に耳を傾けます。
このとき一方的に注意するのではなく、体調不良や家庭の事情、交通機関の乱れといった原因を把握することが重要です。
改善に向けた目標設定と支援

遅刻の原因が特定できたら、次はその原因に応じて、具体的な改善策をメンバーと一緒に考えます。
例えば健康上の問題がある場合は医療機関の受診をサポートしたり、通勤方法の見直しを助言したりすることが望ましいです。
また親の介護など、家庭の事情によって定時の通勤が困難になっている場合、休職を提案することも視野に入れましょう。
メンバーが一時的に離脱するのはチームビルディングにとって痛手ですが、離職してしまうよりはまだ負担が少ないです。
行動記録と注意喚起の文書化
どれだけ改善を促しても遅刻が続く場合、遅刻の記録を取り、口頭の注意だけでなく書面で注意喚起を行うことを検討します。
これにより、本人の自覚を促すことができますし、後の懲戒処分を行う場合の根拠にもなります。
懲戒処分の検討
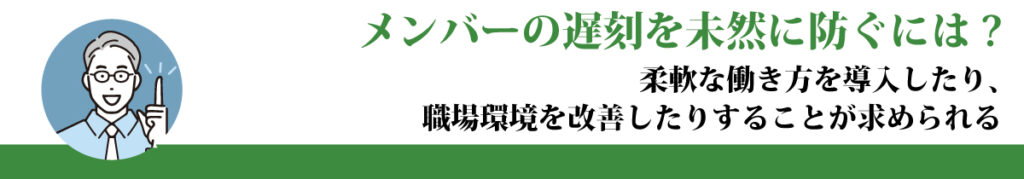
再三の指導にもかかわらず改善が見られない場合、就業規則に則り、減給や出勤停止といった懲戒処分を検討します。
ただし、処分の内容は慎重に判断し、いきなり解雇とするような過度な対応は避けなければいけません。
メンバーの遅刻を未然に防ぐには?
チームビルディングのメンバーの遅刻を未然に防ぐには、柔軟な働き方を導入したり、職場環境を改善したりすることが求められます。
柔軟な働き方とは、従業員の多様な状況に対応するため、フレックスタイム制度や時差出勤制度などを導入することを指しています。
これにより、すべてのメンバーが同じ時間に業務を開始する必要がなくなり、遅刻の根本原因を解消できる場合があります。
ただし柔軟な働き方を実現するには、現場の状況を把握し、業務に支障が出ないようにマニュアルを整備しなければいけません。
またメンバーにおける遅刻の背景には、職場に対するモチベーションの低下や、人間関係の問題があることも考慮します。
心理的な側面に配慮し、働きやすい環境を整備することで、遅刻の減少につながります。
例えばメンバー間の関係性が良くない場合、院長先生が間に入り、各メンバーの意見を聞いた上でベストな体制を整えます。
もし上司や院長先生に意見がしにくい環境なのであれば、風通しを良くするために、上司や院長先生から積極的に各メンバーとコミュニケーションを取ることが大切です。
ちなみに、院長先生は必ずしもすべてのメンバーの遅刻状況をリアルタイムで把握できるとは限りません。
そのため、正確な勤怠記録を自動で行う勤怠管理システムを導入し、遅刻の状況を客観的に把握することも重要です。
まとめ
チームビルディングだけに限らず、社会人は組織で行動しなければいけないため、頻繁な遅刻は言語道断です。
しかし、メンバーを叱責するだけでは、根本的な解決にはつながりません。
メンバーにも言い分があるケースや、正当な理由が存在するケースもあるため、まずは面談を行うことが大切です。
また3up Projectを受けさせることにより、医療従事者の基本的な心構えを再認識させることも検討しましょう。