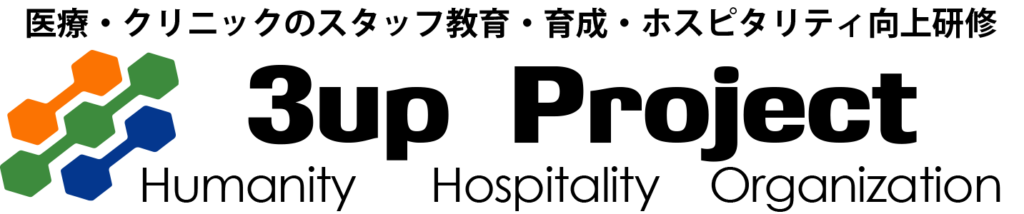クリニックのチームビルディングにおける散会期とは、主にプロジェクトの完了により、チームが解散する最後の段階を指します。
チームが解散すると、また新たな目標に向けてチームが結成されます。
しかし、散会期にはトラブルが発生することもあります。
今回は、具体的にどのようなトラブルのリスクがあるのかを解説します。
チームビルディングの散会期におけるトラブル4選
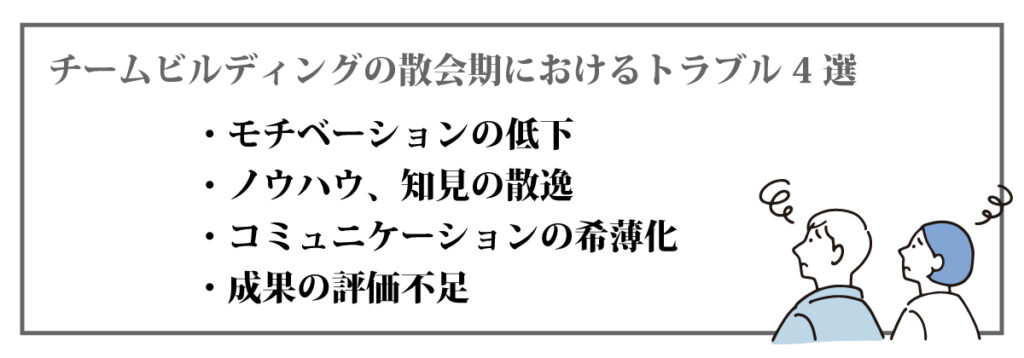
クリニックのチームビルディングにおける散会期では、主に以下のようなトラブルが発生することがあります。
・モチベーションの低下
・ノウハウ、知見の散逸
・コミュニケーションの希薄化
・成果の評価不足
各項目について詳しく説明します。
モチベーションの低下
チームビルディングの散会期は、どうしてもメンバーのモチベーションが低下しやすいです。
具体的には、メンバーの関心が次の業務に移ってしまい、現在の業務への熱意が失われがちです。
特にチームの解散がすでに決定している場合、貢献度が評価されにくくなると感じ、やりがいを失うことがあります。
もちろんこのようなモチベーションの低下は、最後の最後で目標達成までに時間がかかってしまうことや、次のチームの結成にも悪影響を及ぼすことが考えられます。
ノウハウ、知見の散逸
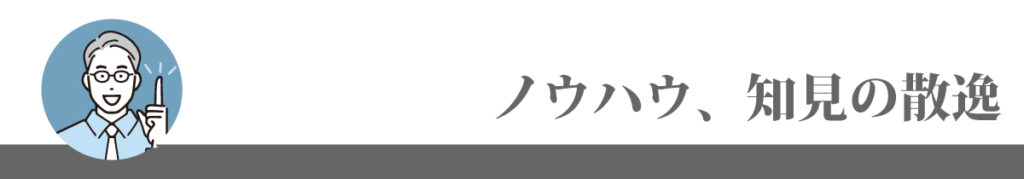
チームビルディングの散会期は、基本的にすべてのメンバーが同じ方向に向かい、目標を達成した上で満を持して解散することが望ましいです。
しかしメンバーの方向性がバラバラのまま目標を達成してしまうと、ノウハウや知見の散逸が起こります。
具体的には、プロジェクトを通じて学んだ成功体験や失敗から学んだ教訓が、適切に文書化・共有されないままチームが解散することがあります。
これにより、次のプロジェクトで同様の課題に直面し、非効率な作業を繰り返すリスクが高まります。
コミュニケーションの希薄化
散会期を迎え、プロジェクトが完了するとなったとき、メンバー間のコミュニケーションが減少し、感謝やフィードバックが行われなくなることがあります。
このように感謝の気持ちを伝えられないまま解散すると、メンバーは満足感を得られず、経験がネガティブな記憶として残ってしまうことが考えられます。
またチームビルディングは、クリニック内の従業員で構成されますが、一度終了しても各従業員は同じ院内で勤務し続けます。
そのため、散会期にコミュニケーションが希薄になると、今後の人間関係にも支障が出てくる可能性があります。
成果の評価不足
チームビルディングの散会期において、目標の達成を急いでしまうと、最終的な成果の評価や文書化が不十分になることがあります。
これによりチームが何を生み出し、どのような貢献をしたのかが曖昧になり、達成感が薄れてしまいます。
チームビルディングの散会期におけるトラブル対策
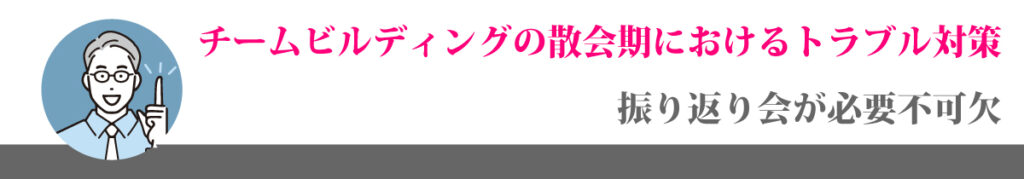
散会期にはチームの成果を祝い、学びを次につなげるための振り返り会が必要不可欠です。
またメンバー同士が互いの貢献をたたえ合い、感謝を伝えられる場を設けたり、院長先生から労いの言葉をかけたりすることも大切です。
さらにプロジェクトの成功要因や達成した目標を具体的に共有し、チーム全体の達成感を高めることも意識しましょう。
院長先生はチームビルディングのリーダーとして、数字やデータだけでなく、メンバーの頑張りも言語化して賞賛することが求められます。
まとめ
チームビルディングの散会期は、すでにゴールが見えている状態であるため、ついつい院長先生を含めメンバーが気を抜きがちです。
そのため、キレイな形でチームビルディングを一旦終わらせることができるよう、早い段階から体制を整備しておきましょう。
なかなか目標を達成できず、散会期にまで達することができないというケースでは、従業員教育の一環として3up Projectの活用も検討すべきだと言えます。